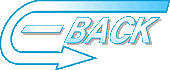第1回 おジャ魔女どれみシリーズ
−上級編−
鷹羽が『どれみ』で最も評価している方向性について触れよう。
前述の『クリィミーマミ』や『マジカルエミ』のような使命を持たない魔女っ子物は、一般に作品中で魔法をもてあます傾向がある。
『マミ』当時、スタッフがアニメ誌のインタビューに「“セブンが邪魔だ!”状態になっている」と答えているのがその一例だ。
これは、『ウルトラセブン』のスタッフが番組制作に当たって“ストーリーを充実させた結果、セブンを活躍させられなくなる”という本末転倒な事態に陥っていたという話を引用して、魔法を絡めて話を作るのが難しいと言っているのだ。
現実世界を物語の舞台に据えた『マミ』や『エミ』の場合、ありふれた日常を描こうとすればするほど魔法が遊離してしまう。
かといって、スポンサーが魔法のアイテムを商品として売り出している以上、全く登場させないというわけにもいかない。
「“セブンが邪魔だ!”状態」というのは、魔法を使う必然性を絡めて物語を作ることの難しさから出た悲鳴だと思う。
特に『エミ』の場合、主に魔法を使うのがエミへの変身とマジックショーでのマジックの部分だけであり、魔法が邪魔者になっていた感が強い。
それだけに、『エミ』最終回3部作では、主人公:舞が“魔法を使わずに魔法のようなマジックをしたい”から魔法を捨てるという選択が描かれた。
魔法それ自体を軸にしない自由度の高さが、却って作劇を難しくしている一例だろう。
『どれみ』シリーズでも似たような部分はあって、時折魔法を使わない話がある。
特に、見習い服とパティシエ服がリバーシブルになっている『も〜っと!』では、お菓子に魔法の粉を振りかけるという行為自体が魔法のアイテム使用シーンとして利用されることもあって、見習い服になるのはホウキに乗って空を飛ぶためだけということが結構あった。
そんな中でも、『ドッカ〜ン!』40話『どれみと魔女をやめた魔女』は、もう1つの最終回とも言えるほどテーマ性が強く、魔法を全く使わず、しかも変身すらしないというかなりの異色作で、鷹羽はこのエピソードが大好きだ。
そして反対に、魔法の絡め方が非常に上手く、光っている話も多い。
鷹羽の場合、そういう話が見たくて『どれみ』シリーズを見続けていたような部分がある。
特に、『も〜っと!』44話『あいちゃんが帰っちゃう!?』や、『ドッカ〜ン!』9話『はづきのキラキラ星』での魔法の使い方は秀逸だった。
『あいちゃんが帰っちゃう!?』では、あいこの父の勤めていたタクシー会社が倒産した関係で、あいこが大阪にいる母に引き取られることになり、どれみ達4人は、あいこを引き留めるためにマジカルステージを使う。
その結果、なんと求人情報誌がバサバサと降ってきたのだ。
結局、その情報誌を読んでタクシー会社の求人を見付けることで、あいこの父は無事再就職でき、あいこは東京にいられることになった。
そのタクシー会社が玉木の父の経営するもので、玉木の父が“あいこを育てた人なら人柄の点でも安心”という理由で迎え入れるくだりも、単なるご都合主義にならない演出だった。
魔法は無茶苦茶しょぼいが、ことが“再就職”という現実的な内容だけに、あっさり魔法で解決とならなかったことがとても嬉しい。
また『はづきのキラキラ星』では、心臓の手術を受けるクラスメートのしおりを励ますため、手作りの髪飾りをマジカルステージで手術室の彼女の手元に送る。
手術を成功させること、心臓の病気を治すことは魔法ではできないから、“治ってほしい”というエールを送り届けたわけだ。
これは、客観的には無意味とも言えるが、どれみ達の主観としては十分意味があり、また、励ましたいという気持ちを送るという意味では、しっかり役目を果たしている。
要は見舞いに千羽鶴を持っていくようなものだが、“直接手術室内に送る”ことで魔法を使う必然性も持たせてある。
また、『どれみ』の特徴として、所謂大人の事情というものをさらりと描いていたりもすることも挙げられる。
『も〜っと!』15話『きれいなお母さんはスキ? キライ?』では、父を早くに亡くした母子家庭の長谷部たかしを中心に、小料理屋を営む母が化粧して店に出掛ける姿を嫌悪していた長谷部が、母を理解し和解する過程を描いている。
長谷部は、酔っ払い(父以外の男)の相手をするために化粧をしている母の姿に、子供らしい怒りを感じているのだが、母としては、夫の遺した店を大切にしたいわけで、この辺に気持ちのズレがある。
この状況下で、どれみは、魔法を使って彼をハムスターに変え、一緒に小料理屋へと忍び込む。
そこで長谷部は、働く母の姿を見、母が偶然吐露した自分への愛情溢れる言葉を聞き、母へのわだかまりを解くことになる。
どれみ達が説教するのではなく、また、面と向かって母から諭されるのでなく、偶然母が心情を吐露する場面に出くわすには、やはり普通でない忍び込み方をしなければならない。
その意味で、魔法を使うことに意味があり、なおかつ、長谷部がハムスターに変えられるまでの展開が、“怪しい占い師に言われたとおり亀を助けたら、実は亀は乙姫が化けたもので、助けたお礼にハムスターにされる”というあまりに不条理なもののため、長谷部自身、夢なんじゃないかという感覚を持っていて、魔法であることを上手く隠蔽している。
ちなみに、このエピソードでは、どれみとももこが女子大生に化け、その小料理屋でバイトして事情を探ろうとするのだが、その際、長谷部の母が「私は誇りを持っているけれど、こういう商売は、世間から偏見の目で見られる」という内容のことを言って断っていたりと、「それって子供に分かるの!?」的な描写があるのだが、そういう部分も『どれみ』の特徴の1つなのだ。
こういった複雑な事情は、1回のエピソードでは描ききれないことも多いため、数回に分けて、場合によってはシリーズを跨いで描かれているものもある。
登校拒否児童・長門かよこの一連の話や、ぽっぷのピアノ話などがそうだ。
かよこがどれみと知り合ってから学校に通えるようになるまでには、『も〜っと!』20話『はじめてあうクラスメイト』、38話『学校に行きたい!』、45話『みんなで! メリークリスマス』の3話を使い、間を置きつつ半年かけている。
そして、その後のかよこについてもきちんと描かれており、『ドッカ〜ン!』10話『修学旅行!! 班長はツラいよ』では、彼女はどれみ達とは別の班に入れるまでになっている。
で、当然彼女はどれみに深く感謝しており、『ドッカ〜ン!』最終回での「どれみちゃんと一緒に卒業したいよ!」に繋がるのだ。
ただし、これら連続系の話は、基本的に『#』以降に限られる。
というのも、前述のとおり『無印』時代初期には続編制作を見越してのロングエピソードを作る基盤がなかったせいだ。
ピアノを例に取れば、『#』2話『赤ちゃん育てはも〜たいへん!』で、どれみの母:はるかの口から、プロのピアニストを目指していた彼女が、交通事故で手を痛めたために道を断たれたという経緯が語られるのが最初だ。
その後、19話『どれみとはづきの大げんか』で、どれみが幼稚園の頃はるかからピアノを習っていたことが語られる。
どうやら、はるかは娘に夢を託そうとしていたらしい。
ところが、当のどれみは、一向に上手くならず、5歳の時に初めての演奏会で、緊張のあまり大失敗して深く傷ついてしまった。
自分の夢を押しつけたことでどれみを傷つけたことを後悔したはるかは、ピアノを処分してしまい、ピアノを習いたかったぽっぷがコンプレックスを感じていた。
この状況については、劇場版で語られている。
そして40話『春風家にピアノがやってくる!』のアバンタイトルは、なんと劇場版のラストシーンの続きから始まっており、どれみの口添えもあってはるかは新たにピアノを買い、ぽっぷに教えるようになった。
その後、『も〜っと!』17話『因縁のライバル!! 春風と玉木』で、初ステージで緊張するぽっぷに、どれみが自らの苦い経験を基に、想いを込めたお菓子を作って応援に駆けつける姿が描かれるなどした。
結局、ピアノのネタは、最後のぽっぷ主役編である『ドッカ〜ン!』41話『ぽっぷが先に魔女になる!?』まで描き続けられた。
余談だが、『も〜っと!』序盤のころは、ぽっぷ役の声優:石毛佐和氏が産休を取っており、ぽっぷを登場させられない状況だったそうだが、ちょうどぽっぷが発表会に向けてピアノを練習している期間と重なっており、実に自然にフェードアウトできていた。
また、休業の話とはちょっと違うのだが、オヤジーデ役の松尾銀三氏が『も〜っと!』放送中の平成13年8月25日に急逝したため、その後『も〜っと!』ではオヤジーデがほとんど出演していない。
しゃべれないんだから当然なのだが、続く『ドッカ〜ン!』の1話から、声優を金光宣明氏に変更して何食わぬ顔で再登場した。
『も〜っと!』以降のオヤジーデは魔女幼稚園の下働きをしているので、登場しなくてもちっとも困らないのだが、せっかく浸透したキャラクターを大切にしたかったことから再登場させたものと思われる。
実際に聞き比べてみるとかなり印象が違うが、再登場までに4か月以上のブランクを持たせることで、声優が変わったことにさほど違和感を感じさせなかったわけだ。
同じように放映途中に声優が急逝した例として、『絶対無敵ライジンオー』のタイダー役:吉村よう氏が思い出されるが、後任となった辻村真人氏の声についての違和感を考え合わせると、『も〜っと!』放映中に代役を立てなかったのは正解だったと言えるだろう。
もちろん、『ライジンオー』におけるタイダーは絶対不可欠なキャラクターだったから単純に比較しようというわけではなく、そういった違和感を感じさせないように出番を削ったことに素直に感心しているだけであることをお断りしておく。
ところで、先程こういった連続話について「基本的に『#』以降に限られる」と書いたが、たった1つだけ例外がある。
それがあいこの母親話だ。
あいこの両親が離婚していることは『無印』23話『大逆転!? おジャ魔女の試練』で触れられているのだが、両親の離婚の理由などについては全く語られていなかった。
それについて初めて触れられるのが34話『お母ちゃんに逢いたい!』だ。
ここで、あいこの両親が母の仕事の関係で別れたことが語られ、47話『お父ちゃんのお見合い』で、あいこは母の再婚が自分の勘違いだったことを知る。
そして、続く『#』の20話『お母ちゃんに会える! あいこ涙の再会』で、離婚の真相の一端として流産があったことなど、あいこの知らなかった部分が語られる。
その後、『#』44話『幸せのホワイト・クリスマス』、『も〜っと!』26話『思いよとどけ! あいこ大阪へ』、劇場版『カエル石のひみつ』、44話『あいちゃんが帰っちゃう!?』、『ドッカ〜ン!』15話『お母さんのわからずや!』、38話『ついに再婚!? あいこの決意』、48話『あいこのいちばん幸せな日』と、丸3年以上にわたって描き続けられ、あいこ主役編の最後を飾るほどのロングエピソードとなった。
ただ、これは鷹羽の個人的な感覚なのだが、『お母ちゃんに逢いたい!』の時点では、あいこの母親の話はここで終わらせるつもりだったのではないかと思える。
というのも、この話はあいこ自身が“父と2人で生活する”ことを選択している形で終わっているからだ。
とはいえ、番組として続編を作る上では、やはりおいしいネタであり、母の再婚があいこの勘違いだったことを巧く利用して続編を作ったり、その後もなんだかんだと揉めさせてなかなか再婚させなかったのではないだろうか。
再婚の最大の障害だったあつ子の仕事問題をクリアする決め手が、もうすぐ介護が必要になるであろう祖父という『も〜っと!』劇場版で降って湧いた設定(当事者である父母にとっては分かり切った存在)だったりすることからも、そう感じざるを得ない。
だとしても、何年も経ったが故にようやく和解できるということは現実にもままあることであり、さほど不自然でもなかろう。
いずれにしても、両親の離婚と再婚という非常に重いテーマを3年掛けて描いたということは、アニメという媒体の懐の深さを垣間見せてくれたように思う、というのは言い過ぎだろうか。
ところが一方で、鷹羽が喜ぶようなタイプの作劇は、子供には不評を買うという噂もある。
今回例に挙げた『どれみと魔女をやめた魔女』など、魔法を使ってのドタバタを期待する子供にとってはつまらない回と映るかもしれない。
ことに『ドッカ〜ン!』辺りのエピソードには、子供に不評だったものも結構あったらしい。
確かに『ドッカ〜ン!』19話『お父さんは素直になれない!?』など、家が自営業でなければ全く理解できないのではないかと思われるものもあるし、納得できることだ。
中級編で書いたとおり、『どれみ』のシリーズ終了は玩具の売上不振であって、視聴率自体は悪くなかったらしいのだが、視聴率を支えるのは必ずしも現役の子供とは限らないのだし。
また、こういったエピソードを好意的に受け止める昔の子供達の中には、『ドッカ〜ン!』のことを『おジャ魔女ハナちゃん』と呼ぶ人も多いらしい。
主に目立った行動をするのがハナちゃんで、どれみ達は脇役でしかないという意味を込めた嫌味らしいのだが、実際、主力商品はほとんどハナちゃん関連の物だし、事件を起こすのもハナちゃんであることが多い。
どうしてそうなったのか。
実は、この2つの問題は繋がっている。
どれみ達は過去3作品で様々な事件を乗り越えて成長しているため、今更妙な失敗はそうそうしてくれない。
ドタバタは、主人公が発展途上だからこそ問題が起き、それを収斂していってこそ成り立つのであり、中級編で述べたとおり、主人公が経験を積み成長すると、物語は回らなくなってしまう。
初級編で書いたとおり、番組が長く続くためには、のび太のように同じ失敗を何度でも繰り返せる素養が必要なのだ。
ではどうするか。
『ドッカ〜ン!』は、大きく分けて
| 1 | ハナちゃん中心の物語構成 | |
| 2 | 6本のイバラと無気力の雲 | |
| 3 | ゲスト主体の物語構成 |
1つ目のハナちゃん中心の物語構成は、要するに上で書いたおジャ魔女ハナちゃんだ。
つまり、どれみ達が成長したことで、スタッフは、主人公を思いっきり未熟な存在に変えたのだ。
ハナちゃんは、その物怖じしない性格と世間知らずとから、今のどれみ達なら起こさないような問題を次々と起こしてくれる。
そして、保護者であるどれみ達は、騒動を収束させるために奮闘せざるを得なくなる。
これが『おジャ魔女ハナちゃん』と呼ばれる原因となったエピソード達だ。
ハナちゃんの天真爛漫ぶりが鼻につく人は、これを理由に『ドッカ〜ン!』を嫌うようになったりもしたという。
2つ目の6本のイバラと無気力の雲は、ストーリーの縦糸として存在するため、どれみ達は否応なく騒動に巻き込まれていく。
ただし、女王にアイテムを届けるのはハナちゃんだし、後半の主力商品であるパオちゃんとアコーディオンが無気力の雲を撃退する方法となっていたことから、ここでもハナちゃんがどれみ達を食っている感がある。
だが、どれみ達を中心に据えつつ、ハナちゃんを主人公にしない方法がある。
それが、3つ目のゲスト主体の物語構成だ。
どれみ達の友人をその回だけの主役に据えて、見守りつつ手助けする役をどれみ達にあてがえば、ハナちゃんを前面に押し出すことなくどれみ達が行動できる。
ただし、それでもやはりゲストが目立つことになり、結局どれみ達は前3作ほど物語の牽引力になれないのだ。
このパターンが、現役の子供に最も不評だったらしい。
さらに、大きなお友達からも「主人公がどれみである必然性がない」とまで言われることもあったと聞く。
ドタバタコメディには、トラブルメーカー的存在が不可欠になる。
そして、『無印』では主にどれみが担っていたその役目が、『ドッカ〜ン!』ではハナのものになっている。
これは、前述したとおり、どれみ達が成長した結果、トラブルメーカー足り得なくなってしまったからだろう。
それ故に、どれみ達おジャ魔女チーム以外でトラブルメーカーが必要になってしまった。
結果、新たなトラブルメーカー:ハナがおジャ魔女の1人として登場し、どれみ達はトラブルシューターの役を担うことになった。
『ドッカ〜ン!』17話『秘密基地を守れ!』を見ればよく分かる。
このエピソードは、上の2つ目と3つ目の複合形式の話で、恐らく「主人公がどれみである必然性がない」と言われかねない作りになっている。
内容としては、クラスメートの宮前達が人力飛行機を作っている秘密基地のことをハナが不用意に漏らしてしまったために先生にバレてしまい、飛行機が没収される前に宮前が無理矢理飛ばして墜落する、というものだ。
この“先生にバレた”ところからが物語の山なわけだが、どれみ達分別のある者なら、絶対に秘密を漏らしたりはしなかったろう。
ここで、ことの重大さを理解していないお子様であるハナの存在が必要なのだ。
『ドッカ〜ン!』でハナに白羽の矢が立ったのは、『#』からの登場でキャラクターとして浸透していること、世間知らず故の悪意のないドタバタを起こしやすいこと、どれみ達と別系列の商品展開に持っていきやすいことなどからと思われる。
『ドッカ〜ン!』の続編企画として、『おジャ魔女ぽっぷ』の名が上がったのも、既にどれみ達では主役を張れる状況になく、視聴者に続編だと認識してもらえる新たな主人公を立てる必要性からの苦肉の策だったはずだ。
かつて週刊少年ジャンプに連載され、アニメ化までされた『まじかる☆タルるートくん』というマンガがあった。
分かりやすく言うとドラえもんの亜種のような作品で、のび太同様のダメ人間:江戸城本丸(えどじょう・ほんまる)を助けるために、本丸と契約した魔法使いのタルるートが、様々な魔法アイテムを使って騒動を起こす、というのが大まかな筋なのだ。
ところが連載元がジャンプということもあって、本丸はアイテムを使って特訓してしまう。
例えば、サッカーが上手くなりたい本丸はアイテムで手と足を入れ替えてもらい、手で歩き、足で物を食べたりできるよう特訓する。
たしか試合では足を負傷した本丸が、特訓で手で歩けるほどの腕力を得たことを生かし、逆立ちしたまま足でボールを保持して走るといったシーンがあったように思う。
このように、本丸は何か事件がある度に成長したため、とうとうタルるートの魔法を必要としなくなってしまったのだ。
それでも漫画の人気はそれなりに高かったこともあって、連載は続けなければならない。
そこで、作者は設定を一旦リセットすることにした。
タルるートの新たな契約相手を登場させ、舞台そのものを移すことで連載を続けようとしたのだ。
ところが、新たに契約相手となった岸麺太郎(きし・めんたろう)は、本丸とキャラがかぶらないように作られたため、成長した本丸との落差も相まって、非常に感情移入しにくい存在だった。
そのせいかマンガ自体の人気が失速し、なし崩し的に最終回となってしまった。
このように、主人公を下手に変えると、作品としての連続性すら失われてしまうので非常に危険なのだが、『どれみ』は主人公総入替でもしないと、既に続編制作すらおぼつかない状態だったのではないかと思われる。
前述のゲスト主体の物語構成は、主人公をどれみのままで作劇する最善の方法であったのではないだろうか。
恐らく、『どれみ』に更なる続編を作った場合、問題になるのは、誰をトラブルメーカーに据えるかということになっただろう。
ちなみに、先程の秘密基地の話では、どれみ達の魔法は、冒頭でハナの後を尾けて秘密基地を発見したときにしか使っていない。
事件自体は、魔法によって収拾されたわけではないし、どれみ達がしたことは、秘密を漏らしたハナを諭したことと、宮前の飛行機の助走を手助けしたことだけだ。
たしかに『どれみ』の物語である必然性には乏しい。
ただ、鷹羽は、“主人公がどれみである必然性がない”とは決して思わない。
既にキャラクターが確立されたどれみ達だからこそ、友人の世話を焼いて何かをするに当たって余計な説明が不要になり、作劇がすっきりするからだ。
もちろん、こんな作劇は何度も使える手ではないし、2年続けたら飽きられるだろう。
『どれみ』は、やはりこれ以上続けられなかった作品なのだと思う。
ともかく、こうして『どれみ』は終わりを告げた。
鷹羽が『どれみ』を愛してやまないながらも、「もっと続編を!」と言う気にならないのは、“これ以上どれみ達を引っぱり出さなくても、また良質な作品を作れるはず”という想いと、“綺麗に物語を締めてほしい”という想いとの複雑な交錯によるものだ。
たしかに、鷹羽の好むような話が子供達に理解できるかという問題はある。
だが、たとえ今すぐは分からなくても、何らかの強い印象を与えることができたなら、心のどこかにしまい込まれることだろう。
それは、やがて見直すチャンスがあったときなどに、「これってこんな話だったのか!?」と再認識させてくれるかもしれない。
- 魔女っ子物の体裁を取りながら、
- 『無印』ラストでは、魔法ではなく心が大切だと気付き、
- 『#』では魔法を使わずに子育てし、親として子に対する無償の愛を知り、
- 『も〜っと!』ではお菓子に様々な想いを込め、
- 『ドッカ〜ン!』では手作りの品物を作り上げていく
といった具合に、魔法であっさり何でもするということを否定し、努力して生きていく姿を描いた『どれみ』。
鷹羽は、『どれみ』はアニメ史に残る名作足りえる可能性を秘めた作品だったと思っている。