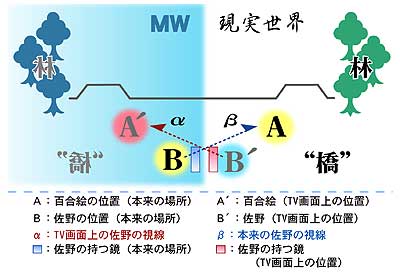
| ・ | 鏡、金属壁等反射物を通して行き来できる左右逆の異世界 |
| ・ | そこには人を食うモンスターが住み、時折モンスターは現実世界に現れて人を襲う |
| ・ | モンスター以外の動物は存在しない |
| ・ | ミラーワールドへ行き、かつ現実に戻ってこられるのはライダーだけ |
| ・ | そのライダーもミラーワールドに長時間居続けることはできない |
| ・ | ミラーワールドで破壊された物が、ある時は現実世界でも破壊され、ある時は破壊されない |
| ・ | 水面のような水平に存在する反射物も出入口になるが、上下は逆転しない |
| ・ | 人間はいないのに、乗り物はちゃんと移動する |
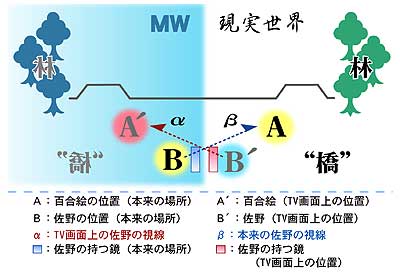 |
| ←BACK |
| →NEXT |