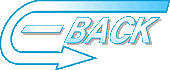
第2回 宇宙刑事シャリバン
−上級編− 『宇宙刑事』シリーズは、3作品とも同じ脚本家の手によるため、脚本家サイドでも作品ごとの色分けをしようとしているようだ。 マクーが一般的な犯罪組織だったのに対して、マドーは「幻夢城」という言葉に象徴されるように亡霊的イメージを与えられており、フーマは宗教団体的な組織になっている。 初期設定では、マドーは超能力者による犯罪組織であり、その長たる魔王サイコは機械的に超能力を増幅しているエスパーということになっている。 恐らく「マドー」という名称は魔道にちなんでいるのだろう。 だからこその魔王サイコなのだ。 サイコの名前自体もサイコキネシスからだろうし、幹部であるドクターポルター、ガイラー将軍の名称もポルターガイストと、いずれも実体がないのに物を動かす現象を意味する言葉から付けられていると思われる。 …と書いたら、元締から「魔王サイコは、そのものずばりサイコから来てるんじゃないの?」との指摘を受けた。 結局、詳しいことはわからない。 番組中では超能力者集団というイメージは失われたが、姿を消しては背後から攻撃するといった“こちらと思えばあちら”的な部分には亡霊的表現が生き残っているし、サイコが人工頭脳によって超常能力を発揮しているということも作中で明言されている。 ちょっとソースが思い出せず自信がないのだが、当初は「幻夢」ではなく「幻魔」にしようとしたが「幻魔大戦」に引っかかるのでできなかったという話もあったように思う。 他方、シャリバン側としては、俗に「奇星伝」と呼ばれているイガ星再興物語が年間の縦糸となっていく。 奇星伝が始まるのは19話と遅かったが、それ自体は当初から予定されていたのだそうだ。 なんでも、「伊賀電」という名前を考えたのはメイン脚本の上原正三氏で、イメージとしては伊賀忍者の末裔であり、それではスケールが小さいから宇宙規模の伊賀ということで“イガ星の末裔”にしたらしい。 上原氏によれば、『ギャバン』が“父探し”という内的な目的に向かった反省から、『シャリバン』では外的な目的:星再興物語にしたとのことだが、視聴者からは「シャリバンは自分の星のことばっかり一所懸命やっている」という批判もあったらしい。 批判とは直接関係ないが、実は『シャリバン』は視聴率的にはあまり良くない。 中盤登場のレイダーは、精神面で電を苦しめるという役どころで、力押しでない強さと怖さを見せており、口元を隠し、見えるのは眼窩のくぼんだ目元だけ、低くてちょっとこもった感じの口調、青白いライティング、滑るような移動など、正に幽鬼のようなキャラクターだった。 レイダー役の安藤三男氏(故人)は、『キカイダー』でプロフェッサー・ギルを演じた人だが、ギルのヒステリックさとは正反対の抑揚を少な目にした演技で、“こいつ何かしでかすぞ”という印象を与え、スタッフが狙った以上の怖さを体現してくれた。 ところが、これが裏目に出てあまりの怖さに子供が番組を見なくなるという大誤算を生んでしまった。 これ以降、視聴率は下がったとのことで、平均視聴率は『ギャバン』の14.9%に対し12.9%となっている。 残念ながら最高視聴率がいつで何%だったかについて今となっては分からないが、当時のスタッフのインタビューによると、それまで好調だった視聴率がみるみる下がったのだとか。 テレビ朝日系金曜夜7時半と言えば、本来7時からの『ドラえもん』を見た小さな子供がそのまま見てくれる時間帯であり、本来そういった視聴者をそのまま『シャリバン』に誘導したかったのに、ハイブロウな作品にし過ぎて「『ドラえもん』の視聴者層を蹴散らしてしまった(スタッフ談)」のだそうだ。 東映は、これによほど懲りたらしく、次作『シャイダー』では、主人公を極めて明るいキャラにした。 何しろ、沢村大はディスコに聞き込みに行って「ジュース!」と注文し、しかも「僕は宇宙刑事です」と自己紹介してしまうキャラで、大きなお友達からは「(番組が)ガキ向けになってしまった」と不評を買ったのだが、その分、メイン視聴者層である子供を取り戻した。 しかも、森永氏演じるアニーがパンチラの嵐を吹かせたので、お父さんが一緒に見てくれるようになって、かなり視聴率が回復したらしい。 当時、ファンの間では『宇宙刑事』シリーズの中で『シャイダー』の評価が極端に低かったのだが、それにはこういった背景があった。 また、敵組織である不思議界フーマも、幹部構成を物静かな中性的キャラの神官ポーと荒々しい武人のヘスラー将軍にしている。 続く『ジャスピオン』に登場する魔女ギルザは、呪いでジャスピオンの魂を抜いたりするレイダーと同タイプの位置づけながら、ハキハキとしゃべるキャラになっていて、陰湿な怖さを避けて通っているようだ。 『スピルバン』終盤に登場するヨウキも、敵組織ワーラーに中途参加する幹部で“最期には組織乗っ取りを画策し処刑される”というレイダーと重なる設定だが、やはり女性的なキャラで、陰湿で物静かだが怖いキャラではなかった。 さて、『シャリバン』は、1980年代トクサツ番組ベスト3のアンケートをやれば大抵選ばれる作品だし、鷹羽もベスト3を選べと言われたら間違いなく入れるが、最近の作品しか見たことのない人に、無条件で傑作と薦められるかというと難しい。 というのも、東映トクサツは毎年の作品の反省点などを盛り込みながら常に進歩し続けているため、20年前の作品ではどうしても粗が目立つからだ。 1話完結が当然だった20年前において、前作『ギャバン』の設定を受け継ぎ、奇星伝という年間の縦糸を盛り込んで完結させたことは驚嘆に値する。 しかし、1年を通じて伏線を張りつつ最後にまとめ上げたのかと言えばそうではない。 例えば、イガクリスタルや親衛隊達は、20話で行方不明になった後、実に半年以上経った49話でようやく再会している。 その間、彼女らが画面に出たのはほんの数回と、ラストスパートまで放置されていた感が強く、やはり1話完結的な要素の方が表に出ている。 毎回の展開にしても、 「幻夢界に引きずり込め!」(幻夢界発生)
というバンク使用の“毎度お馴染みのパターン”があり、意地悪なお友達からどうしてグランドバースで魔怪獣を倒さないんだという突っ込みを受けることになる。↓ モトシャリアンを呼ぶ↓ マドー戦闘機と小競り合いして撃ち落とされる↓ シャリンガータンクもしくはグランドバースを呼んで戦闘機撃破↓ マドーの戦艦出現↓ マドーの戦艦撃破↓ 魔怪獣(怪人)と等身大戦闘なにしろ幻夢界には自分達しかいないんだから、一般人に巻き添えを食わせる心配もないのだ。 毎回名乗りポーズを入れるのもこの時代の通例で、“高いところで名乗りを上げる”というヒーロー物の王道が毎回繰り返されていた。 宇宙刑事シリーズの場合、最終話近辺を除くと毎回、変身の後に名乗りと変身プロセスの説明が流れる。 この流れは普段は大変好ましいものだが、時と場合によっては邪魔以外の何者でもなくなることがある。 ベル・ヘレンが死ぬ42話『戦場を駆け抜けた女戦士の真っ赤な青春』がそれだ。 このエピソードは、登場以来数話にわたり電と共に戦ってきたヘレンが、レイダー配下の女戦士に騙し討ちされて非業の死を遂げるというものだ。 ヘレンは、“自分がマドーに捕らえられて隠れ家を白状したために恋人を失った”という過去を持っているため、恋人を失ったという刺客の言葉に同情して警戒を怠り、不意打ちを食らってしまったのだ。 なんとか刺客は倒したものの、電が駆けつけたときには既にヘレンは虫の息となっており、「ごめんね、シャリバン」と、油断した自分のミスを詫びる。 電は、抱きかかえたヘレンを降ろした後、取り囲む戦闘員達を睨み据え、走りながら「うおおおっ! 赤射ぁっ!」と変身して戦うのだ。 このとき、渡氏は映画『スーパーマン』でロイスを喪ったスーパーマンを参考にしながら演技をしていたそうで、ヘレンに対する優しいまなざしと、その後に敵を睨む怒りの表情の演技は非常に評価が高い。 渡氏は、後のインタビューでこのときのことについて、“赤射と言わずに「うおおおっ!」と叫びながら敵に突っ込んで変身したかったが、言わないと変身できないから仕方なかった”とコメントしている。 これはつまり、怒りに燃える電が叫び声を上げつつ走り出したときに、「赤射!」と叫ぶことなく変身して戦い始めたかったという意味だ。 それほどまでにこのシーンでは怒りを表現したかったわけだ。 ところが、ここで定石が邪魔になってしまった。 怒りに燃え、敵に向かって走っていたはずの電は、定石どおり、変身するなり高いところに飛び上がり、「宇宙刑事シャリバン!」と名乗りを上げる。 このときの名乗りは怒りに満ちた声であり、電の怒りの描写はなんとか維持されるのだが、なんとこの後さらに赤射プロセスの解説まで入るのだ。 これでは、電の怒りの描写は途絶えて、後は普通の戦闘シーンになってしまう。 これ以降のことになるが、スーパー戦隊シリーズでは、心情描写を優先するなどの目的で、変身コードなしで変身したりすることが時たまある。 『ダイレンジャー』15話『3バカサッカー!』で、妹を人質に取られ1対11の不利な試合を強要されたリュウレンジャー:亮が押し殺した声で「気力…転身」とつぶやくと共に変身ブレスのオーラキーがひとりでに伸びるシーンは、普段は手で引っ張り出しているキーがどうして勝手に伸びるのかという疑問すら吹き飛ばし、亮の押さえた怒りの重さをよく表現していた。 (注:亮は念動力のような力を持っているので、伸びてもおかしくはない) 『シャリバン』当時、そういう演出は考えられないようなパターン破りだったのだ。 せめて解説だけでも入らなければ、流れが寸断されることはなかっただろう。 ちなみに、翌年の『シャイダー』23話では、電波妨害のために「焼結!」と叫んでもバビロスに届かない状況下で、アニーが大の居所を目視し、手動システムでプラズマブルーエネルギーを照射して焼結させている。 要するに、大の意思に関係なく焼結させることができるのだが、このときでさえ大は「焼結!」と叫んでいる。 こうしないと視聴者である子供に理解できないという判断だったわけだ。 この辺は、昨今の作品を見慣れた目には時代遅れな演出に映るのも仕方ないし、撮影技術だけでなく演出技法なども過去の作品を踏み台にして進歩している以上、当然と言える。 撮影用コンバットスーツなども、『シャリバン』ではアップ用とアクション用の出来の落差が大きく、“アクションシーンになると(コンバットスーツが)段ボールみたいになる”と言われていた。 『3人の宇宙刑事』のスチールを見ると、ギャバンの手の装甲が黒手袋の甲側に手の形のウレタンを貼っただけのものであることが分かる。 模様は、そのウレタンに描かれているだけで特段凹凸もない。 特番とはいえテレビに映る以上、それなりの衣装を用意しただろうに、指先まできちんと装甲が覆っていないスーツしか揃えられなかったのだ。 今のようなアップ用に遜色のないアクション用衣装を見慣れた目からすると、正に隔世の感があるだろう。 初級編で触れたホシノスペースカノンにしても、『ギャバン』開始当初から張られた伏線ではなく、全44話中42話で初めて出てきた設定だ。 それまでは、ボイサーが囚われている理由については特に語られておらず、ただ単に“囚われた父の行方を追っていた”に過ぎない。 電の登場も同じ42話であり、重傷を負ってバード星に運ばれた電が、わずか2週間で完治した挙げ句宇宙刑事になっているのも、意地の悪い言い方をすれば“繋がりを作るためにラストで出しただけ”に過ぎない。 『シャイダー』では、沢村大は能力を認められスカウトされて、約2年にわたって訓練を受けているにもかかわらず“訓練途中の任命”という扱いになっており、19話ではコム長官から「はっきり言おう。君は未熟だ」まで言われてしまった。 そのため、ファンの間から「じゃあ、シャリバンはどうだったの?」と疑問の声が上がったものだ。 このように、どちらかというと1話完結的な面が強い性格上、縦糸話も十分に機能しているとは言い難く、今見れば中途半端のそしりは免れまい。 ただ、それでも『シャリバン』は、今見ても十分光る部分を持っている作品なのだ。 レイダーの造反劇の伏線はかなり前からちびちびと張られており、38話辺りからは、レイダーがマドー乗っ取りのために色々策を弄していく様が描写されている。 また、ラスト4話(1か月)をかけて、最後のイガクリスタル争奪戦から最終決戦までを上手に盛り上げ、綺麗に終わらせたことは間違いない。 初級編でも書いたが、伏線の処理をしきれずに終わることが今でも多い東映トクサツにおいては、これはかなり凄いことなのだ。 スタッフ的にも非常にノッていて、イガ星絡みの話など電の心境に大きな変化のあった回などでは、EDの歌詞が2番になっていたりしていた。 ちょうど『ASTRO-BOY鉄腕アトム』の後期で、青騎士編などロボットの心絡みの話でEDがバラードバージョンになっていたようなものだが、20年前でそれをやっていたわけだ。 鷹羽が知る限り、最終回以外でEDをいつもと違うバージョンで流すなんてのは『シャリバン』が初めてだったと思う。 個人的なことを言わせてもらうと、鷹羽が『シャリバン』をリアルタイムで見たのは最終回だけなのだが、このたった1話が鷹羽に与えた影響はとんでもなく大きい。 以前にも書いたことがあるが、放送時間の関係などもあって、鷹羽は『ギャバン』中盤ころからトクサツを見ていない。 そんなころ、以前『気分屋な記聞』に書いたとおり、この当時新潟にテレビ朝日系列のNT21が開局し、放送中だった『ダイナマン』と『シャリバン』が正規の時間帯に移動した。 そのお陰で、土曜夕方6時からの『ダイナマン』は、ゼノビア登場辺りから見られるようになったのだが、『シャリバン』の方は金曜の夜7時半ということで、相変わらず見られないままだった。 今の感覚から言うと、「じゃあビデオ録りゃいいじゃん」と思うかもしれないが、そうはいかない時代背景というものがあったのだ。 当時はまだビデオデッキの普及率が低く、鷹羽の家にビデオデッキが入ったのは83年の秋ころだったし、その頃120分テープは1本2千円前後していた。 また、当時のビデオデッキには1週間に1番組の予約しかできない機種も多く、鷹羽の家にあったのはそういう“使えない”デッキで、鷹羽はTBS系で7時から放送していた『銀河漂流バイファム』を“撮っては消し”で見ていたため、チャンネルの違う『シャリバン』を録ることはできなかったのだ。 ところが、ちょうど『シャリバン』最終回の前の週に『バイファム』の第1部が終了し、第2部からは時間移動することになったので、“せっかくだから最終回くらい見ておこう”と思い見てみたところ、これまで見ていなかったことを激しく後悔することとなってしまった。 『バイファム』も面白かったので、“『バイファム』録らないで『シャリバン』録ってりゃ良かった”とはならないのだが、家族に泣きついてでも録ればよかったかなぁと思ったものだ。 前作である『ギャバン』は、1話完結の単発話の中に“父探し”というサブテーマを絡め、ラストで再会・死別・敵討ちを果たした。 父探し話がそうしょっちゅう絡んできたわけではないが、多分東映トクサツでサブテーマを持たせてきちんと解決させたのは初めてだったと思う。 残念ながら、父がどうして囚われていたのかという理由付けについては、ラストで急遽決まったようで、作品として綺麗に終わりきれなかった感もある。 そして『シャリバン』は、『ギャバン』から引っ張ってきたホシノスペースカノンの話に15話で決着を着けた後、19話からサブテーマである“イガ星再興”の物語を始め、27話のイガ星人マリオの裏切り、36〜42話のイガ星戦士ベル・ヘレン編などを絡めながら、48話からのラスト4話でまとめ上げた。 この意味で『シャリバン』は、1話完結の単発話の中に、年間の縦糸となる話を具体的に絡めた最初の作品であると言えるだろう。 この1年後、『ジャスピオン』では、宇宙の悪サタンゴースを倒す鍵となる“黄金の鳥”探しが1年掛けて絡められていくし、『チェンジマン』では、途中で出てきたゲストが終盤で再登場したり、いくつものきっかけを重ねて敵幹部が次々裏切っていく大河ドラマが展開する。 『シャリバン』は、そういった作品が登場する土台ともなった東映トクサツの金字塔の1つなのだ。 |