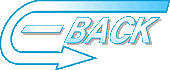
|
第1回 おジャ魔女どれみシリーズ
−中級編− このシリーズでは魔女になろうとするどれみの物語が描かれているわけだが、特に『無印』の設定には目を見張るものがある。 目標である魔女試験合格のためには、9級から1級までの試験に合格しなければならないのだが、当然、試験というからにはそれなりの試練が与えられ、それを魔法でクリアすることが必要になる。 そして、 試験に合格するためには魔法の使い方が上手くなければならない
▼ 1.魔法を上手く使えるようになるには練習しなければならない▼ 2.魔法を使うには魔法玉を消費しなければならない▼ 3.魔法玉を入手するには、魔女界から仕入れなければならない▼ 4.魔法玉の代金は、MAHO堂でアイテムを売ったお金で払わなければならない M ももこ(『無印』『#』時代はマジョリカ)
A あいこ H はづき O おんぷ DO どれみ という具合で、どれみ達5人の名前はMAHO堂と合致する。 ちなみに、どれみの企画時の名前は「おんぷ」だったそうだ。 こういう、ネタが先にあって名前が決まるというパターンは、魔女のネーミングに結構多いようだ。 どれみ達に機織りを教える魔女はマジョクロス(布)だし、『も〜っと!』ラストで幻のレシピのケーキ作りを争った魔女はマジョバニラだった。 また、『#』でハナの健康診断を受け持っていたのはマジョハート(心臓)なわけで、全部がそうというわけではないが、その背景を名前としている魔女は多い。 先々代の女王:マジョトウルビヨンもその1人で、彼女の場合、ケーキのトゥールビヨン(フランス語で渦巻き)に引っかけている。 女王様ともあろうお方が「渦巻き」なんて名前なのは少々笑えるが、これは“プロポーズに同じ名前のケーキを送った”という展開にするためにしたものだろう。 ところで、実は時計の部品にもトゥールビヨンというのがあったりする。 機械式腕時計(電池を使わない時計)の中でも1000万円以上のクラスには、より正確に時を刻むためにトゥールビヨン脱進機という機構が組み込まれているものがあるのだ。 番組スタッフとしてはそこまで考えてはいなかったはずだが、時間の流れによって生じた不幸を背負った女王に時計のパーツと同じ名前が使われているのは、偶然の一致としてはできすぎだろう。 ちなみに、フランス語のtourbillonには、「渦巻き」のほかにスラングで「落ち着きのない人」という意味もある。 分かってつけたならとんでもない話だ。 ほかにも、進級試験の試験官であるモタとモタモタは喋るのがのろいのが特徴だが、彼女らが『#』で育てていた赤ちゃんの名前は、テキとテキパキとなっている。 ゲストキャラクター・タコの八太郎とイカのスルメ子の間の子供がアタリメ子だったりするのも、やはり拘りだろう。 ネーミングの話からは若干外れるが、『無印』最終回は『さようならMAHO堂』、『#』最終回は『さよならハナちゃん』、『も〜っと!』最終回が『さよなら魔女見習い』で、『ドッカ〜ン!』の実質的最終回である50話は『さよなら、おジャ魔女』という具合に、最終回のサブタイトルもほぼ統一されていたりして、スタッフの拘りが仄見える。 さらに余談だが、どれみ役の千葉千恵巳氏とその父親役の望月祐多氏には、どちらも千葉麗子氏とある程度の期間一緒に仕事をしているという奇妙な繋がりがある。 もちろん、だからといって両者に面識はなかっただろうが。 望月氏は『恐竜戦隊ジュウレンジャー』でティラノレンジャー・ゲキを演じており、千葉麗子氏はプテラレンジャー・メイを演じている。 一方、千葉千恵巳氏がアイドル崩れでヘアヌード写真集を出したことがあるのは有名だが、彼女がその直前まで所属していたアイドルユニット「オーロラ5人娘」のリーダーは芸能界引退直前の千葉麗子氏だったりする。 当時鷹羽は、『ジュウレンジャー』後のチバレイの動向としてオーロラ5人娘を知ったのだが、その後、泣かず飛ばずのまま解散してメンバーの1人がヘアヌード、という怒濤の展開を「あらあら」とか思って見ていた。 その写真集は、発売直後ころ既に古本屋に1,600円くらいで並んでいるのを見た記憶があるが、当然の如く『無印』放送中には高値になっていたそうだ。 ちなみに、「オーロラ5人娘」という名前は、『巨人の星』に登場する架空のアイドルユニット:オーロラ3人娘にちなんで付けられている。 そういえば、おんぷ役の宍戸留美氏も元アイドルだった。 彼女は、『KO世紀ビースト3獣士』でヒロインのユーニ・チャーム・パスワードを演じ、OP曲『恋はマケテラレネーション』などを歌っているほか、平成8年に『どれみ』と同じ時間帯で放送された『ご近所物語』で、ヒロイン幸田実果子の声を演じ、OP曲『ヒ・ロ・イ・ン』を歌っていた。 彼女は、割と最近まで自分で営業からマネージメントまでしていたそうで、一時はヌード1歩手前までいっていたのだが、すっかりメジャーになってしまった。 もしかしたら、彼女のセミヌード写真集も今頃は高値なのかもしれない。 話を『どれみ』本編に戻そう。 前述のとおり、どれみ達は修行中の身なので、大した魔法は使えない。 だが、大した魔法を使えないということは、いざというとき役に立たないということでもある。 この部分でも、マジカルステージという“数人で力を合わせて大きな魔法を使う”方法を持たせた意味は大きい。 これは要するに合体必殺技であり、複数の魔女っ子が登場することに意味を持たせ、全員のアイテムを画面いっぱいに映し、仲間の団結を示し、映像的な見せ場を作り、1人では使えないような大きな魔法を使うことに説得力を持たせるという効果があった。 必ずしも全員揃う必要はなく、1人や2人抜けていても使える点や、逆にぽっぷなどが加わることができるという点も作劇上とても有効だった。 もっとも、それでもさほど大きな魔法は使えなかったのだが。 また、『ドッカ〜ン!』で顕著なのが、“心を込めた手作りの良さ”を前面に押し出していることだ。 これは、先々代の女王に、孫のために色々なものを作っていたころのことを思い出してもらうことで、悲しみのイバラを消し去るというテーマに付随している。 『も〜っと!』でも、作ったお菓子の仕上げとして、想いを込めた魔法の粉を振りかけるという場面があったが、『ドッカ〜ン!』ではそれを1歩進めて、作る過程で真心を込めていくという過程を大切にすることを描いていた。 どれみ達に機織りを教えたマジョクロスは、魔法を使えば何でも簡単に作れるのに、わざわざ時間を掛けて手作りすることの意味を先々代の女王から教えられている。 『美味しんぼ』で海原雄山が「人を感動させることができるのは、唯一、人の心だけなのだ」と言っているが、心を込めて作られたものを見て何かを感じるということは、一般生活上、ままあることだ。 魔法で何でも簡単にできる魔女だからこそ、心を込めて手作りすることの意味が理解できない。 前述のマジョクロスが変わり者として扱われているのは、その意味で彼女が異端だからだ。 そして、だからこそ女王は、“孫との思い出の品”を再現するのは魔女には不可能と考えて、自分の命を削ってまで“人間であるどれみ達”に賭けたのだろう。 いささか綺麗事ではあるが、人の心身に直接的な影響を与えることなく、心をもって問題を解決するという点で、『も〜っと!』も『ドッカ〜ン!』も非常に良心的な作品だった。 ところで、この“女王の思惑”というのは、『#』冒頭でどれみ達がハナの誕生に立ち会うよう導いた段階で、既に見え隠れしている長大な伏線であり、人間の感覚を持つ魔女という特異な存在を生み出すことで人間界と魔女界を融和させるという、女王の長年の夢をどれみに託したということなのだ。 彼女がどれみにそこまで入れ込んだ理由については、『ドッカ〜ン!』ラストでいきなり明かされるため、いささか唐突な感が否めないが、2度にわたって魔女の資格を失ったどれみをその度に魔女見習いに戻したという行動そのものが、女王の期待を何より雄弁に物語っているだろう。 そして、彼女が保険医の姿でどれみの動向をずっと見守っていたということが、そこに説得力を持たせる。 その意味で、女王がゆき先生であることをラストまで引っ張り続けたことには価値がある。 傍で見ていたからこそ、あのドジなどれみにそこまで期待を掛けていたのだ、と。 そして、このシリーズは、ハナを除く全員が魔女になることをやめ、人間として生きる道を選んで幕を下ろす。 最終回では、卒業式の日、仲間との別れを悲しんでMAHO堂に籠もったどれみが、みんなに励まされ、何の取り柄もない思い込みの激しいドジな女の子が、実は誰よりも優しく、真っ直ぐで一所懸命で誰にでも好かれる女の子であることに気付くまでを描いている。 そして卒業式のシーンに合わせて、ED曲『わたしのつばさ』のどれみ達合唱バージョン1番が流れ、どれみの あたし、世界一不幸な美少女じゃなくって、世界一幸せな美少女だったんだ! というモノローグを挟んで、2番をバックにいつものEDクレジットが流れる。 最後は、『無印』OP曲『おジャ魔女カーニバル!!』が流れる中、その後のはづき達4人の姿がそれぞれ映り、制服姿のどれみが誰かにラブレターを渡して終わる。 “魔法に頼らず自分の力で告白する勇気”を手に入れ、少し大人っぽくなったどれみの姿をもって、4年間続いた物語は幕を閉じた。 タイトルが変わっても、作品のテーマを見失うことなく紡がれてきた良質な物語だった。 |