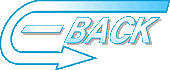
(有馬 真)(ありま・しん)
有馬神社の先代神主にして、葉桐、柚鈴の父親。
人知れず魑魅魍魎を滅する神威(かむい)の戦士だったが、葉桐の母が堕ち神の末裔であることを知らぬままに愛し合い、葉桐が産まれた。
そのころ頻発した神隠しの犯人を見付けられぬまま、十数年後に再び起きた神隠しの原因を突き止めた真相は、妻が葉桐のために殺していたという事実…。
神に仕える身が、堕ち神などという穢れたものと暮らし、しかもその妻と娘が人を殺していたことが、真の心を打ち砕いた。
顔の半分をえぐられ、左手を失ってようやく妻を殺したものの、娘を殺すに忍びなく逃がしてやったことが後悔の種となる。
一旦自分で逃がしておいて何故とも思うが、これは恐らく一哉とのことを知ったためだろう。
前述のとおり、葉桐は、一哉が沙久耶と結婚した後も逢瀬を続けていた。
真は、このまま行けば、自分が見逃したばかりに再び堕ち神の子の犠牲者が出てしまう…そう考えたのだろう。
だが、覚醒している葉桐を相手に正面から勝つほどの力は残っていない。
だからこそ、有馬の血を引く沙久耶を強姦して神威の血(=有馬の血)を濃く引く禁断の子供を産ませようとしたのだ。
真も一哉も、同じように妻が堕ち神の末裔であることを知った人間なのに、どうして真だけが神社の結界に阻まれるのか?
それは、1つには、真の方が格段に霊力が強いからだろう。
強い力を持つが故に、結界に阻まれるのだ。
だからこそ、より一層自分の身が穢れるのを承知の上で下法の技を使って悠志郎を生みだした。
真の感覚では、悠志郎は道具であると同時に可愛い息子でもあるらしい。
自分の失った穢れなき霊力を持っている便利な道具だが、同時に自分の血を引く存在であるだけに、できることならば目覚めさせないままに人としての人生を送らせてやりたいとも思っていたようだ。
柚鈴シナリオでの「お前の人生を生きさせてやれる」という言葉は、そういうことだと思う。
その一方で、柚鈴はあくまで悠志郎を生み出すための原料でしかなかったようで、一欠片の愛も見せていない。
“穢れ”というものに対して純粋でありすぎたことが悲劇を生んだのだ。
(嘉神悠志郎)
柚鈴から生み出された神威の戦士。
それ故に柚鈴と惹かれ合うらしい。
きちんと肉体を持っているのだが、柚鈴と精神的に同調することで本当に一体化してしまう性質を持っている。
柚鈴シナリオでは、初めて柚鈴とHしたときに生で中出ししたらそのまま融合してしまった程だが、美月シナリオでは、その性質が物語に大きな意味を持つ。
悠志郎の魂には、真が植え込んだ暗い想念が眠っており、真の呼び掛けで目覚めるようになっている。
また、真は柚鈴を操り悠志郎と融合吸収させることで、悠志郎の力を自在に振るえるようになっており、昔悠志郎を作った後、わざわざヌケガラになった柚鈴を返したのは、いざというときのための安全装置だったのだろう。
全てのシナリオから、真が狙った方策を考えてみると、まず自力での美月襲撃と葉桐を呼び出しての対決、それが叶わないようなら悠志郎を目覚めさせての美月抹殺、悠志郎が操れないなら柚鈴に吸収させて利用、という順番のようだ。
まだ目覚める前の美月を殺すのを中心に考えているのは、理に適っている。
だが、この中で葉桐との対決だけが異彩を放っている。
はっきり言えば、年月を経て力が衰えている真では葉桐に勝つのは難しいし、美月が死ねば一応問題は解決するのだから、これは作劇上の方便だと思われる。
美月のシナリオでは、柚鈴と悠志郎の関係を前面に押し出せるが、ほかのシナリオでは柚鈴と悠志郎が融合する展開に持っていくのは難しかったのだろう。
つまり、葉桐と真の対決は、柚鈴を介さないでストーリーを進行させなければならないという必要性から生まれているのだ。
かといって、覚醒しているはずの葉桐が死に損ないの爺にあっさりと敗れるようではストーリーの重さそのものが吹っ飛んでしまうから、あれはギリギリの調整なのだろう。
実は、悠志郎の存在はこのゲーム最大の謎の1つだ。
一哉が悠志郎の正体を知らなかったこと、そのくせ悠志郎の父と古くからの知己であること、柚鈴から作られた悠志郎が鈴香より年上であること、などから考えると、元々存在した悠志郎という子供を消し去って、下法で作った悠志郎と入れ替えたということだろうか。
元からいた子供を核として柚鈴から力を抜いて現在の悠志郎を作ったにしては、柚鈴と悠志郎が融合したときに元々の悠志郎が混じっていないということは考えにくいのだ。
だとすると、実の親にも見分けが付かないほどに巧く偽の記憶を与えて入れ替えたということになる。
どうもミスっぽいんだけど。
(有馬柚鈴)
真曰く「悠志郎の絞りかす」で、真が沙久耶を強姦して身籠もらせた娘。
沙久耶の夫だった一哉は、当然そのことを知っていたようで、生まれてきた柚鈴に対して恐ろしく冷淡な態度を取り続けている。
そして、そういった幼児体験と、悠志郎という分身を削り取られたことによるアンバランスさが対人恐怖症に繋がっているのだろう。
鷹羽的には、突然父が倒れたために帰郷する悠志郎に柚鈴が付いていってしまうというエンディングが一番のハッピーエンドだと思う。
実際問題としては、美月の体質という問題がある以上はその後に問題が起きないはずはないのだが、悠志郎・柚鈴という重要な手駒を失った真は、大したアクションを起こせず、美月は無事大人になってしまいそうなのだ。
真にできることは、葉桐を何とか引っぱり出して戦いを挑むことだけであり、多分敗れて死んで終わりだろう。
このエンディングでの、柚鈴の“愛する人と一緒に生きるために見知らぬ世界に飛び込んでしまった”蛮勇は、評価に値すると思う。
また、美月を琥珀に封印して、曲がりなりにも姉妹が全員生き残るなど、出生以外に不幸な設定を持っていない分だけ、柚鈴のシナリオは前向きなものが多い。
4つあるエンディングの全て、なんとバッドエンドですら彼女は成長しているのだ。
(有馬美月)
堕ち神の末裔にして、本作最大の悲劇の主人公。
本人に全く落ち度はないのだが、存在そのものが悪という存在だ。
悠志郎とケンカを繰り広げながらもいつの間にか惹かれ合っているというラブコメ全開なシナリオだが、考えようによっては怖い話だったりする。
葉桐が言っているとおり、堕ち神は、年頃になると自分が精を受けるべき対象を見定めることになる。
ということは、そのころ近くにいる男の中から抱かれるべき男を決定すると言うことだ。
この場合、美月の周囲で最も気の置けない相手が悠志郎だったということで、言い方を変えれば、本人が意識していないだけで、『一番食欲をそそる相手が悠志郎だった』とも言える。
いや、そういうのを『好みの問題』と言うのかもしれないのだが。
ともかく、存在そのものが人間に害をなす以上、美月に純粋なハッピーエンドはあり得ない。
短命なこと、悠志郎の精を受けねば生きていけないこと、子供を作るわけにはいかないこと、この3点は曲げられない条件なのだ。
ベストエンドと思われる(ED曲が流れる)エンドでは、美月がそれを悠志郎に打ち明けた上で結ばれている。
逆に言えば、この条件を飲めるならば、美月は悠志郎と結ばれてもいいのだ。
そう考えると、美月を人間にするために柚鈴が消えるエンディングは、妙であることが分かる。
このエンディングでは、美月は悠志郎の精を受けることを拒否して衰弱している。
ここで柚鈴がすべきことは、美月の呪縛を砕くことではなく、悠志郎と美月に先の条件を提示することだ。
少なくとも、“柚鈴を犠牲にして子供を産めるようになった”などというトラウマを与えることではないだろう。
これで悠志郎と結婚できたとしたら、美月はかなりの偽善者だと思う。
(有馬鈴香)
一哉と沙久耶の娘で、病に倒れた一哉に代わって有馬神社を切り盛りしている。
対人恐怖症の柚鈴がいるというのに、一哉が男(悠志郎)を手伝いに呼んだことに反発している。
ただ、祭の準備には絶対に手助けがいることもよく分かっているため、悠志郎を追い出そうとする美月に「悠志郎さんがいてくれないと困ります」と言い切ってみせるくらいの分別がある。
こういう、現実を見極めた上で、自分の気持ちを抑える術を持ったキャラクターというのは、この手のゲームには少ない。
まぁ、そんな人ばかりだとストーリーが進まなくて困ることになるのだが。
そんな鈴香が、マイペースでのほほんとした悠志郎に惹かれていく様子が微笑ましい。
柚鈴シナリオでは、柚鈴の想いを優先させようとして、行動がドタバタしている。
社務所で仲睦まじくする悠志郎と柚鈴を見て、いきなり怒りだしていなくなってしまう展開にフォローがないのは、“解答は後で”という意味なのだろう。
柚鈴のシナリオクリアの後で鈴香シナリオへの道が開くのは、そういうことだ。
シナリオ的に最も救いがないのも鈴香のシナリオであり、一哉と柚鈴は葉桐に殺され、葉桐は真と相討ちになり、美月は自ら鈴香の短刀に貫かれて死んだ。
結果、鈴香は悠志郎と共に国外脱出することになっている。
鈴香にとって、一哉は沙久耶がいながら外に女(葉桐)を作った不誠実な男であり、葉桐は沙久耶から一哉を奪った憎い女であり、柚鈴は父の違う妹、美月は腹違いの妹だ。
鈴香は、行き場のない寂しさを、柚鈴に愛を注ぐことで支えていたわけだが、飄々とした悠志郎に惹かれていく自分に気付き、その一方で柚鈴が悠志郎に惹かれていくことにも気付いている。
そして、悠志郎の行動によって、自分が柚鈴を守ってきたことが、逆に柚鈴を過保護にしてきたことだということにも気付いてしまった。
これによって、鈴香は自分が依って立つ場所を失ってしまうことになる。
そして、柚鈴を殺した仇であるはずの葉桐が、家族で撮った写真を大事に懐に入れていたことから、二律背反に襲われた。
悠志郎に支えられなかったら、本当に崩壊しかねないほどに追い詰められていたのだ。
鈴香は、美月のシナリオでも柚鈴のシナリオでも、守るべき対象を失ってひとりぼっちになってしまう。
やっぱり一番割を食った人生なのだ。
(幸野双葉)(ゆきの・ふたば)
本編中は攻略不能で、番外編である探偵編で攻略できる。
…が、はっきり言って蛇足だった。
中途半端に本編の設定を引きずるため、イマイチ内容が把握しづらい。
そもそも暗闇を怖がる探偵なんて、いていいのか?
簡単にまとめるつもりだったのに長くなってしまったが、それだけ情報量が多いということでご勘弁願いたい。
各キャラクターの性格や設定などは、番外編を除く全てのシナリオでほぼ統一されている。
例えば、一哉が悠志郎と最初に話をしたときに鈴香との結婚話が出てくるが、この話しぶりに、一哉にとっての3人の娘との距離が如実に表れている。
一哉は“鈴香を嫁に貰ってほしい、婿入りしてくれてもいい、なんならほかの娘でもいいが、美月はやれない”と言っている。
美月と柚鈴の年齢差ははっきり語られていないが、ほぼ同い年で、せいぜい2才違いがいいところだろう。
一哉が美月は駄目だと言う理由は、年齢のことよりも、大事な娘をよその男に渡したくないという父親としての意見だと思われる。
メインの鈴香に関しては、婿取りという形で残るのもいい、ということであると同時に、嫁に出してしまっても惜しくないということでもある。
現実問題として、鈴香がいなくなったら神社の経営が成り立たなくなるという前提があるにもかかわらず嫁に出す気になっているのは、20代半ばという鈴香の年齢などから焦る父親の心と、自分を軽蔑している鈴香へのうとましさが混じり合った結果だろう。
そして、ここでは柚鈴の名前は出てこない。
「ほかの娘でもいい」が「美月は駄目だぞ」となれば、『ほかの娘』に該当するのは柚鈴しかいない。
にもかかわらず、名前を出さないのは、一哉の認識では柚鈴が“その他大勢”だからだ。
その一方で、柚鈴シナリオで悠志郎が危篤の父の元に戻ろうとするときには、早く柚鈴を迎えに来てほしいとも言っている。
これは、別段厄介払いをしたいわけではなく、自分の手を離れて幸せになる道があるなら、それを祝福しようというくらいの愛情はあるということだ。
決して世間体だけを気にして柚鈴を育ててきたわけではないのだろう。
一哉にとって、大事な娘は自分の血を分けた鈴香と美月だけだが、柚鈴は“大切ではないが疎ましいと言うほどでもない娘”なのだ。
随分勝手な考え方のようだが、真にしろ葉桐にしろ、“一番大切なもの”のためにほかの“大切なもの”を犠牲にしていくという究極の選択、つまり極限状態で噴出するエゴがこのゲームの悲劇の本質だと思うので、一哉のエゴなど、そう大層なものでもない。
むしろ、そういったきれい事で収まらない部分をクローズアップしたというのが、このゲームのいいところだと思う。
ところで、このゲームは大正時代の物語ということになっている。
確かに、真の妄執に代表されるように、現代を舞台にするには少々前時代的な部分が多いから、現代劇にはしにくかろう。
鈴香シナリオでの、船で外国に逃げる2人というエンディングも、戦前の移民ブームを背景にしたものだ。
だが、大正時代にするには、キャラクターが現代的すぎる。
例えば、鈴香シナリオで、悠志郎が警察官に随分となめた口を利いているが、戦前で官憲相手にあんな口の利き方ができるわけがない。
同様に、目上の男子に平然と蹴りかかる美月の行動も、あの時代に生きる少女としては異常だ。
自前のカメラで気軽に家族写真を撮り、『明日、街の写真屋で現像してきます』などと簡単に言っていたり、そうやって現像したであろう写真群の中に葉桐のセミヌード写真があったりするのも、時代考証のミスといえるだろう。
どちらかというと、古い因習が残る土地、あるいは古くから使命を受け継いできた家柄というものを背景にしておけば、大正時代でない方がしっくりくる物語だ。
これが大正時代に設定された最大の要因は、“外の世界を知らない”柚鈴というキャラクターだろう。
町並みを遠くから眺め、いつかそこへ行くことを夢見ていた柚鈴が、初めて等身大の町並みに立つシーンは、柚鈴シナリオの大きな見せ場となっている。
だが、テレビが発達している現代では、大抵の場所は家にいながらにして、そこに行ったかのように見ることができる。
もちろん、テレビで見るのと自分の目で見るのとでは意味が大いに違うわけだが、それでも“全く見たことがない”のと“テレビでしか見たことがない”のとでは天と地の開きがある。
また、現代ならば、見たことのない料理であっても簡単にレシピや材料が手に入るわけで、ライスカリーを食べたい一心で恐怖を乗り越えて街へ出ていくという柚鈴の行動は根幹が崩れ去る。
だからこその大正時代なのだ。
あまり細かいところに拘らなければ気付かない程度のミス、というよりは、気付いていた上で、プレイヤーの感覚に合わせて敢えて補正しないまま通したのだろう。
と言いつつ拘るところが鷹羽流なのだけれど。
ところで、恐らく狙ってのことと思うが、鈴香と柚鈴、葉桐と美月の顔が似ていたのは、制作者側の拘りが感じられて良かった。
垂れ目がちな鈴香と柚鈴の姉妹、吊り目がちな葉桐と美月の母子といった感じで、血の繋がりを強調している。
また、鈴香、柚鈴という具合に「鈴」の字を入れた名前で統一されているのは、母 さくや の命名だからだろう。
そういった細かな点での拘りが非常に心地よい。
セーブポイントが少ないこと、エンディングの再生機能がないことなどのマイナス部分を差し引いても、とても楽しくプレイできたゲームだった。
番外編以外は。
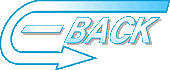 |